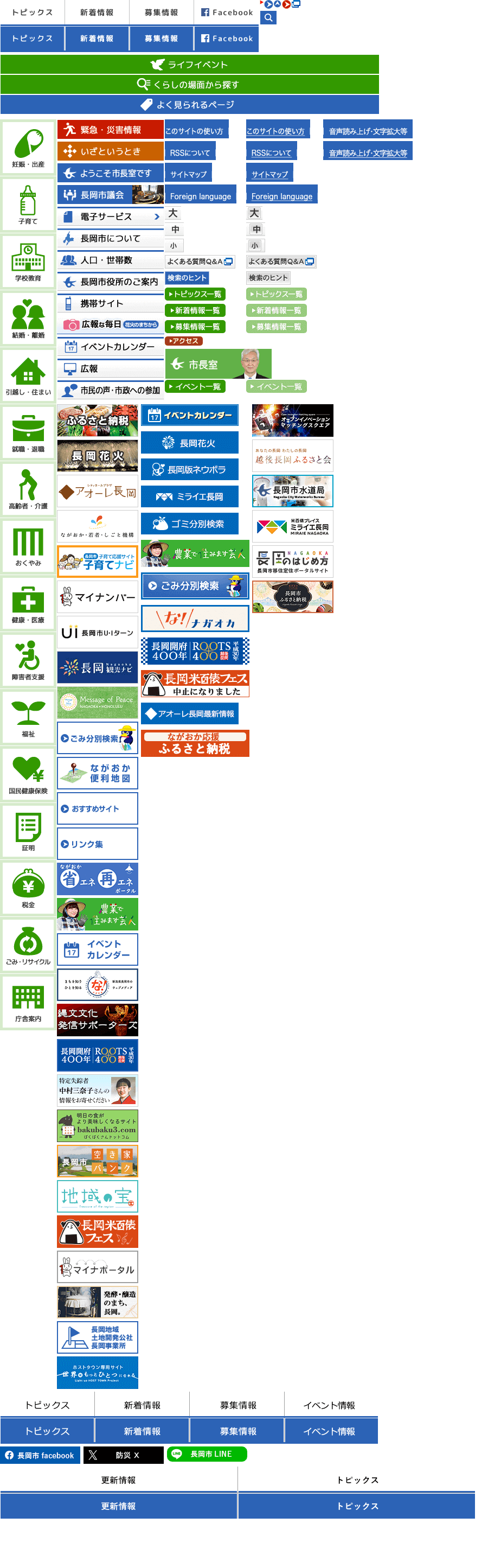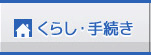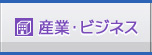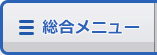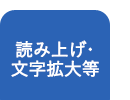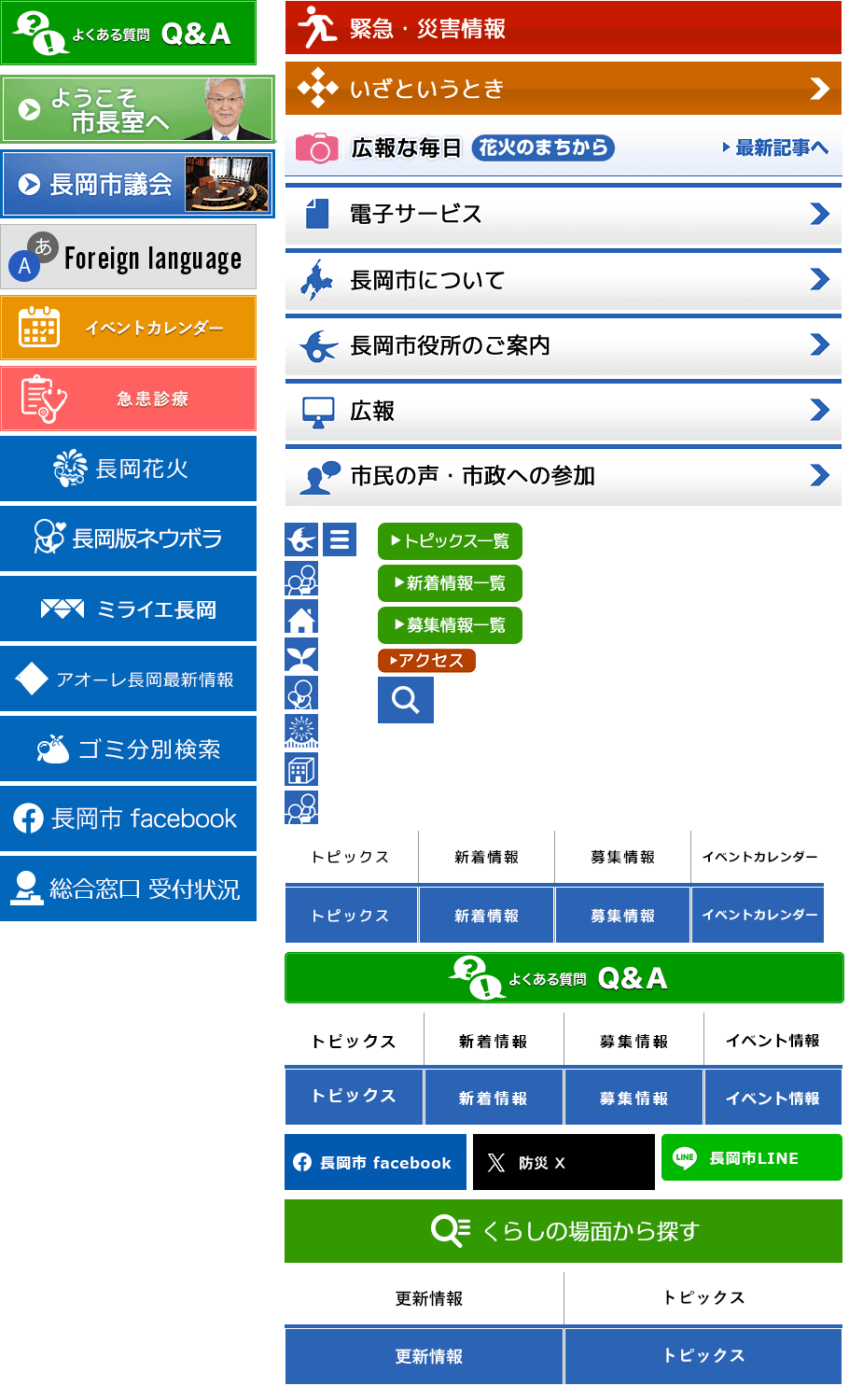令和6年度 主なご意見と回答-その他
最終更新日 2025年6月20日
- 原発30km避難に付随して、都市計画道路 四郎丸ー永田線の早期完了のお願い(令和6年12月)
- 固定資産税の免除期間について(令和6年11月)
- なんちゃってバリアフリー(令和6年10月)
- 町内祭り、町内会の指導、意見を聞かない町内会について、認可地縁団体の認可解除について(令和6年10月)
- アオーレ地下駐車場について(令和6年10月)
- TV東京「なんでも鑑定団」について(令和6年10月)
- 地方創生について、寺泊地区の人口減について、コンパクトシティについて、市有地売却処分について、本庁と支所の仕事について(令和6年9月)
- 中之島に7.13水害の慰霊碑を(令和6年9月)
- 事務事業公開のお願い(令和6年8月)
- 長岡でのくらしをよりよくしたいです(令和6年8月)
- 令和6年5月の日本共産党との関係についての手紙の回答に対する質問(令和6年8月)
- 法令違反の原発(令和6年7月)
- 行政の業務効率化について(令和6年7月)
- 越路河川公園の釣り無償化について(令和6年6月)
- 消防団員の式典による健康被害(令和6年6月)
- 日本共産党との関係について(令和6年5月)
- アオーレ長岡ナカドマの騒音問題(令和6年5月)
- 長岡市としては、○○にアオーレを使うなということですね。よくわかりました(令和6年4月)
- Wikipediaで検索すると表示される長岡市の写真について(令和6年4月)
- ガザ地区における平和の実現を早期に求める決議について(令和6年4月)
お疲れ様です。原発30km圏内の住民の避難が計画されていますが、○○地内は道路が複雑で避難時、困難が予想されます。
今でも朝夕の17号線バイパスや8号線バイパスに出るまでに複雑で困っています。
つきましては、速やかに原発避難できるように都市計画道路 四郎丸ー永田線の早期着工を要望致します。又、計画案があるようでしたら教えてください。
※昔、町内会でも要望を出した時もありますが、ここは原発避難の緊急事案として市長のご英断で話しを進めて頂きたくお願いする所存です。
○○さんが原子力災害時の避難をご心配されるお気持ちはよくわかります。
万が一、原子力災害が発生し、放射性物質が放出される危険性が高まった場合、柏崎刈羽原発から30km圏内の市民の皆さんは、まず自宅等の建物の中で屋内退避となり、その後、放射線量が基準値を超えた場合のみ避難するという計画となっています。
都市計画道路四郎丸町永田線の未整備区間の整備時期につきましては、現時点では決まっていません。○○地区及び川東地域全体の交通状況や、社会情勢等を注視しながら、事業化について検討してまいりたいと考えております。(令和6年12月)
担当:原子力安全対策室
電話:0258-39-2305 FAX:0258-39-2309 メール:gen-an@city.nagaoka.lg.jp
担当:土木政策調整課
電話:0258-39-2307 FAX:0258-39-2273 メール:doboku-seichou@city.nagaoka.lg.jp
まちなか区域外からまちなか区域内に引越したため、固定資産税の免除を受けます。ですが、子どものいる世帯は5年免除に対して、子どもがいなければ3年なのに納得できません。現在不妊治療中です。子どもがほしくてもできません。
子どもがいなければ子育て世帯にすら該当しないのは残念だと思いました。ぜひ、子がいなくても5年の免除を受けさせてほしいです。
本市は、少子高齢化で人口が減少する中、医療・福祉・教育・子育て支援のさらなる充実、イノベーションによる産業振興などにより、中越圏域の母都市としての拠点性をさらに高め、人の流れや企業の拠点分散の受け皿となることで「選ばれるまち長岡」の実現に取り組んでいます。
まちなか居住区域定住促進事業における子育て世帯の税免除(5年間)についても、この取組みの一環によるものです。
現在の制度では、住宅の所有者が住宅に居住した日において16歳未満の扶養親族を有する場合、「子育て世帯」として認定を行っています。
現段階では、子育て世帯の認定条件を改定する予定はありませんが、ご意見は若者定住の支援策として参考とさせていただきますのでご理解をいただきたいと思います。(令和6年11月)
担当:都市政策課 都市・土地政策
電話:0258-39-2225 FAX:0258-39-2270 メール:toshisei@city.nagaoka.lg.jp
長岡市の道路のガタボコや段差、選挙の時のスロープがきつすぎます。
僕は車椅子なのですがよく段差に乗り上げて動けなくなってしまったり、歩道がでこぼこすぎて車道を通らざるえなくて危険な思いをして暮らしています。
そして選挙のたびに小学校の体育館に投票しに行くんですが、仮設スロープが傾斜がきつすぎる、曲がる所も直角で大変でした。職員に助けてもらったのですが一人では投票にはいけない作りになっています。そして○○公民館の傾斜もひどすぎていけません。
いくら車椅子とはいえ、僕は長岡市民です。市民の暮らしをよくするのが市長の仕事なんですよね。8年前から市役所には陳情していますがちっとも改善がなく憤っています。
お願いですからマイノリティを無視しないでください。
車いすで市内を通行するにあたり、安全にかつ快適に利用したいという○○さんの思いをお手紙から受け取りました。
市内の歩道については、昔整備されたものは段差が大きかったり、経年劣化による損傷が生じたりしており、通行にご不便をおかけして申し訳ありません。
そのような箇所は、市内の至る所で発生しており数も多いことから、ご要望をいただいた都度、対応を検討しています。今後も車いすで利用される方のことを考慮し、快適に通行できるよう維持管理に努めてまいります。
また、このたびは、投票所として使用している○○小学校の仮設スロープでご不便をおかけし、心苦しく思っています。
○○小学校の体育館入口には備え付けのスロープがありませんので、選挙のたびに仮設のスロープを設置しています。体育館入口付近は、市道や駐車場に囲まれており、非常に限られたスペースの中で設置しなければならないため、現状のような、市職員等により補助をさせていただくスロープとなっていることをご理解ください。引き続き、リバーサイド千秋期日前投票所などもご活用くださるようお願いします。(令和6年10月)
担当:道路管理課
電話:0258-39-2231 FAX:0258-39-2273 メール:douken@city.nagaoka.lg.jp
担当:選挙管理委員会事務局
電話:0258-39-2241 FAX:0258-39-2277 メール:senkan@city.nagaoka.lg.jp
○町内祭り
町内会は任意の団体・加入といっても、市や関係機関から市政だより配布・寄付金徴収・公園除草・側溝掃除・ごみ収集等の委託を請けている以上は、事実上の市の下部組織と同様ということで、神仏宗教活動は禁止です。よって、神社を祭る町内祭りも禁止ですので、廃止を命令・指導しなくてはいけません。そもそも、戦時中の国家総動員法の流れでできた隣組・町内会は、マッカーサーから廃止命令が出てる訳ですので、町内会自体はうやむやに残ってるだけで、活動自体は最小限にすべきものです。神仏町内活動の町内祭りなどもってのほかですので、廃止命令・指導をしてください。(神仏に基づかない祭りならいいではないか、という詭弁はありえません。あっても子供会のあそびや原信等の何とか祭りです。)
○町内会の指導
町内会のお祭りは禁止してください。中でも認可地縁団体となってる場合は、政教分離とまでいかなくても、信教の自由から参加や役員の強要を控えるように指導くらいはしてください。お祭りの主体である神社の氏子会が解散したあとを町内が引継いで、役員や神輿担ぎの参加、及び寄付・祝儀を強要するに至っては違法状態は明らかです。町内会に参加しないアパート住民も含めて市政だよりの配布や、町内会費徴収・福祉機関の寄付金徴収・公園除草・側溝そうじ・防災訓練等々頼んで町内に義務を押しつけるなら、団体に無責を持つのは当然ではないでしょうか。まず、氏子会のない町内祭りは禁止してください。(長岡まつりの前夜祭で神輿が参加するのは、一般団体なら構わないとしても、神社に発する神輿は政教分離で禁止でしょう。)
○意見を聞かない町内会について
○○町内会(○○会長)において、総会の出席者は役員と班長のみということで、例年は前班長・前々班長・次期班長等の出席も召集されても、班長以外は班長から委任状をとるように町内会長から指示がでています。例年数名の班長の出席だったのも問題ですが、当年の班長だけに至っては一般住民を全く除外の総会で、意見も決済も役員の独裁で不能状態です。数年前からの町内祭りの廃止意見がでてますが、一部で自分の存在価値になってる高齢者のお陰で一向に廃止されません。市はいろいろ仕事を町内に依頼するわりに、問題を相談しても任意団体には指導・意見しませんの一点張りで役立たずです。警察も相手にしないでしょうし裁判を起こすしかないのでしょうか。明確なご返事をお願いします。任意団体ですから、市の依頼事項も全てお断りしても問題ないわけで、見通しがつかなければ、当然のこと住民としては頼むしか能のない役立たずの市の依頼業務は全てお断りとなります。
○認可地縁団体の認可解除について
○○町内会(○○会長)は、現況の認可要件を満たしていませんので認可を取り消してください。要件1の「住民相互の連絡や地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行う」に至っては、総会で一般住民の参加を阻み特定の人間以外は委任状の強要をして、役員の独裁状態としている。町内祭りは数年前から廃止意見があるものを、神社の氏子会を解散した後も、町内住民に祭り準備と参加を強要して信教の自由を損なっている。高齢化と班区分けの不備で班長の成手を維持できなくなっている。等々の問題で住民の意見が反映されてません。住民の意見を反映できない任意の団体である町内会に、市は意見・指導はしないといわれてますが、不適正は地縁団体の認可取消し位で制裁を加えてください。
町内会の運営についてのお手紙を複数いただきましたので、まとめてお答えさせていただきます。
はじめに、町内会は市の下部組織ではなく、同じ地域に住むみなさんの自主的な意思により結成・運営される「任意」の団体です。このため、市では町内の祭りを取り止めるよう指導することはできないことをご理解ください。
次に、町内会の総会について、コロナ禍以降、総会に出席する人数を役員に絞っている町内会もあるように聞いておりますが、ご意見がある場合は、総会に出席していただき、地域のみなさんで話し合ってみてはいかがでしょうか。
最後に、認可地縁団体の認可の取り消しについては、現状で取り消しの要件を満たしているとは判断できかねますので、ご了承ください。
町内会の運営については、まずは町内のみなさんで話し合い、より良い方向を見つけていただきたいと思います。市としましては、町内会の活動が継続できるよう、今後も支援していきたいと考えております。(令和6年10月)
担当:市民協働課
電話:0258-39-2291 FAX:0258-39-2308 メール:simin-kyodo@city.nagaoka.lg.jp
アオーレの地下駐車場への案内看板を付けてください。
また、イベントでセントラル通りを閉鎖の際は、殿町通りからの駐車場への誘導を行う誘導員の配置をお願いします。
アオーレへ手続きに行ったのですが、米百俵祭りの開催される土曜日でありました。普段はセントラル通りから駐車場へ入っていたのですが、通行止めになったため大きく迂回したのですが、周辺道路が渋滞し、使い慣れない殿町通りから駐車場に向かうに当たり、目印がないためとおりすぎてしまい、大きく時間を消費してしまいました。
そして、地下駐車場から帰るに当たり方面別案内看板がそのままなため、看板に従うと帰れないという状態。また、迂回のため殿町通りの通行量が増え、さらに殿町通りから駐車場へ向かう道が信号機のないT字路のため、交差点内に止まる車が多く、出入りに支障をきたしていました。
一、アオーレ地下駐車場入口への案内看板常時設置
二、イベント時はアオーレ地下駐車場への迂回路案内看板設置、出口から大通りへ抜ける看板の臨時修正表示
三、駐車場の出入り口から大通りまでの誘導員配置
四、通行止めに当たり迂回路の表示
イベントで大手通を盛り上げることは良いことですが、イベント時は市役所に来る市民への誘導も忘れずに行ってください。イベント時に通行止めを行った際の交通量調査も検討願います。
通行止めです。あと自分で調べては好きなように迂回しろ。渋滞など知らんというのでは無責任過ぎます。
10月5日の米百俵まつり開催に際し、アオーレ長岡への往来がスムーズにできなかったことをお詫びします。
アオーレ長岡地下駐車場への案内は、セントラル通りから駐車場へ入るルートで各所に看板を常設していますが、米百俵まつりによる交通規制により機能せず、また代替ルートもわかりにくくなっていました。
○○さんのご意見を踏まえ、今後交通規制を伴うイベントを開催する場合は、市ホームページで規制時間帯におけるアオーレ長岡地下駐車場への代替ルートをわかりやすく掲載するとともに、イベント当日に配置する警備員には代替ルートを周知し、来庁者への案内誘導を徹底します。(令和6年10月)
担当:管財課 アオーレ管理
電話:0258-39-7522 FAX:0258-39-2308 メール:kanzai@city.nagaoka.lg.jp
担当:観光事業課
電話:0258-39-2221 FAX:0258-39-3234 メール:matsuri@city.nagaoka.lg.jp
なんでも鑑定団を長岡によびたい!開催したい。昨年11月に応募しています。話題性がないと採用されません。ユニークな笑いをとる物を広く市内から募集して(市政だより)市立劇場で開催したい。私は申し込み済です。
与板が20何年前第1回開催地です。長岡市内はまだ開催していません。是非長岡によびたい。
リサイクルショップ開いて20年。おもしろい物は多数あります。市長もおもしろい物ありませんか?
テレビ東京『開運!なんでも鑑定団』は、お宝の鑑定にあわせて地域の歴史や文化などの魅力も紹介され、長年愛されている人気番組と承知しています。
誘致を希望される同番組の『出張!なんでも鑑定団』のコーナーについては、市制施行や文化施設開館の節目となる周年事業として誘致・開催されるケースが多いようですので、そういった機会に合わせて実現できたらと考えております。
○○さんが申し込まれたお宝鑑定依頼が番組に採用され、お持ちの品物やエピソードをテレビで拝見する機会が来ることを、私も楽しみにしております。(令和6年10月)
担当:広報・魅力発信課
電話:0258-39-2202 FAX:0258-39-2272 メール:inf-prd@city.nagaoka.lg.jp
○地方創生について
地方創生という国策が、何十年も前からあるが、長岡市が考えている地方創生とは、どの様なものか、又、市の政策として実行しているものは何か。その成果はあがっているのか。人口減、公示地価の下落、経済が回っていないと思うがそれに市の政策として対処出来るのか、御伺いしたい。
○寺泊地区の人口減について
寺泊地区の人口減が加速度的に進んでいる。人口1万3千人が8千百人(ここ12、13年位で)になった。市はどうするのか。このままでは地域及び公共交通機関(JR、バス)もなくなってしまうのではないか。市としての対策、政策、今後の考え方等、御伺いしたい。
○コンパクトシティについて
国策としてコンパクトシティがあると思うが、市としては、今現在どの様に対処しているのか。又今後どの様にするのか。各支所は、各支所地域において拠点が1つ、2つあると思うが、そこを重点的に整備して長岡の中心部と道路インフラ等を継ぐようにして、地域がすたれることのない様にして欲しい。
○市有地売却処分について
寺泊地区国保診療所、T.L.C跡地で広大な面積の土地が、管財課によって売払、賃貸として看板が出されているが、具体的にどのように売っていこうとかという案を持っているのか。案もなく売払いも賃貸もできなければ、今後維持管理費(草刈り等)が毎年すごくかかってきて諸経費削減出来ません。その旨回答願います。又、市有地の維持管理経費が増大しているのをどのように御考えでしょうか。
○本庁と支所の仕事について
本庁と支所についての質問ですが、ある案件で寺泊支所、北部事務所に行ったら、それは本庁扱いで本庁に聞いて欲しいといわれ、本庁に行ったら、それは支所の扱いで支所に聞いて欲しいといわれた。どこに行って聞けばいいのかわからない。責任を人におしつけるような、他人事の行政はやめて欲しいと思う。
いただいた市長への手紙(9月3日受理の5通)については、次のとおり回答します。
まず始めに、「地方創生」及び「寺泊地区の人口減」について、寺泊地域では、出生数が大きく減少するなど10年前と比べ20%以上人口が減少しています。長岡市全体をみても、出生数の大幅な減少や、転出者数が転入者数を上回る転出超過による人口減少が続いています。さらなる出生数の減少や転出超過などの人口減少による市民生活への影響は計り知れないという強い危機感を持っており、長岡市全体で取り組んでいくべき課題だと考えています。
そこで、長岡市では、人口減少に歯止めをかけるため子育て環境の充実、若者の就業確保や就労環境の改善、長岡の魅力発信などの様々な施策を実施し、市民生活の向上と産業の活性化をはじめとする地方創生に取り組んでいます。
しかしながら、未婚化、晩婚化などによる出生数の減少、首都圏等への若年層の市外転出などにより、結果的に人口減少に歯止めをかけるには至っていません。
今後も引き続き、若者や女性をはじめとした様々な人材が活躍できる環境の整備を進め、働きながら出産・子育てができる環境の充実や、テレワークなどの柔軟な働き方の推進による魅力的な仕事の創出、就労環境の改善といった本市が持つ施策やサービスの優位性を全国にPRし、新たな人の流れを生み出す長岡市の総合力で人口減少に歯止めをかけるとともに、中越圏域の拠点として都市機能を高めてまいります。
次に「コンパクトシティ」について、○○さんがご心配されている、地域が廃れてしまわないための取り組みは非常に重要です。
国は、人口減少と高齢化の急速な進行下でも「魅力的で活力ある持続可能なまちづくり」を実現するため、コンパクトシティ政策を推進しています。長岡市もこの考えに基づき、市の最上位計画である長岡市総合計画の土地利用構想基本方針に「(2)コンパクトで、広域的な拠点性を高める都市利用」及び「(3)各地域の多様性を活かし、長岡の総合的な魅力を発揮する土地利用」を掲げ、取り組みを進めています。
地域の拠点性を高める取り組みでは、栃尾地域で令和4年にオープンした栃尾地域交流拠点施設トチオーレをはじめ、現在は与板地域や川口地域でも地域交流拠点の整備を進めており、市民交流ルームや図書館、子育て支援施設などが一体となった生活利便性の高い良好な環境づくりを行っています。
また、地域の中心部と都心地区(JR長岡駅周辺の中心市街地から千秋が原・古正寺地区)を結ぶ幹線道路及び公共交通を維持し、多様な個性・魅力を有する地域間での「ひと・モノ・情報の双方向の活発な交流」を促進することにより、地域活力の創出を図ってまいります。
「市有地売払処分」については、市有地の売却や貸し付けができなければ、草刈りなどの毎年の維持管理経費を削減できないというご指摘はごもっともです。
今回お手紙をいただいた市有地につきましては、現在、現地に看板を設置するとともに、市ホームページにて「売却・貸付可能な物件」として公表し、購入や借り受けの希望を募っております。
しかし、これまでに具体的な購入又は借り受けの申し出はなく、市としても早期に売却・貸し付けを進めて収益を得ると同時に、維持管理経費を削減することが重要と考えております。そのため、今後はサウンディング等市場調査の手法を検討しながら積極的に売却・貸し付けを進めてまいりたいと考えております。
最後に、「本庁と支所の仕事」について、支所地域のお困りごとは各支所でお受けし、必要に応じて、地域事務所や本庁と連携しながら対応します。
支所地域にお住まいの方のご相談は、最寄りの支所窓口をご利用ください。(令和6年9月)
担当:政策企画課
電話:0258-39-2204 FAX:0258-39-2475 メール:info@city.nagaoka.lg.jp
担当:都市政策課
電話:0258-39-2225(都市・土地政策) FAX:0258-39-2270 メール:toshisei@city.nagaoka.lg.jp
担当:管財課 財産マネジメント室
電話:0258-39-2211 FAX:0258-39-2325 メール:f-management@city.nagaoka.lg.jp
担当:行政管理課
電話:0258-39-2208 FAX:0258-39-2279 メール:gyoukan@city.nagaoka.lg.jp
20年前7.13水害で刈谷田川堤防が決壊した所に住んでいる78歳の女性です。先月13日は、20年目の節目で追悼式典がとりおこなわれました。市長様もおいでいただき、ありがとうございました。私も一住民として行きました。当時のことを思い涙しました。水害によって尊い命が3名おなくなりになりました。にもかかわらず慰霊碑をたててあげることに誰一人として今まで声があがりませんでした。不思議でした。
20年の時を迎え、風化させない為にも形あるものを後世に残してあげる事が大事と思うのです。言葉だけでは堤防決壊の事の重大さが伝わらないのではないでしょうか?是非、市長様のお力、ご意見をお借りして実現出来る事を心からお願い致します。
私は20年間いつもその事が忘れられませんでした。
中之島地域で3人がお亡くなりになった7.13水害を風化させないために、慰霊碑を後世に残すことが大切という、○○さんのお気持ちはよくわかります。実際に日本各地において、災害や戦争、事故などでお亡くなりになった方々の霊を慰め、教訓を忘れぬよう、地域の住民や団体が慰霊碑を建立された事例があることも承知しております。
市では、発災後、幾度となく地域住民の皆様と意見交換を重ね、水害犠牲者を追悼し、この教訓を後世に伝承するとともに、地域の憩いの場にしたいとの想いから、発災現場に、’04(ラブフォー)中之島記念公園を整備しました。完成後は、毎年、NPO法人キズナの森と中之島ラブフォー隊によって、追悼行事が実施されているほか、地元小学生と地域住民が一緒に、花の種まきや防災講話を行うなど、7.13水害を忘れない取り組みが行われています。
また、公園内には、社団法人長岡法人会中之島支部による「’04中之島記念公園」と、諏訪神社氏子総代会による「村社 諏訪神社跡」の二つの記念碑が建立されており、3人の犠牲や家屋流失などの甚大な被害、復興の歩みなど、後世に伝える碑文が刻まれています。加えて、「村社 諏訪神社跡」の石碑については、国土交通省国土地理院が自然災害伝承碑として地理院地図等に掲載するなど、災害教訓の周知と普及に役立てられています。
このため、市といたしましては、現在、新たに慰霊碑を建立する考えはございませんが、これらの取り組みを地域と一体となって継続していくことで、7.13水害の教訓を風化させることなく、しっかりと次世代に伝えてまいりたいと思います。(令和6年9月)
担当:中之島支所地域振興・市民生活課
電話:0258-61-2010 FAX:0258-66-2238 メール:nknsm-chiiki@city.nagaoka.lg.jp
私は長岡市議会議員の質疑を聴き、事務事業の公開ということに関心を持ちました。行政の運営をより良くするために、税金の使い途を分かりやすく市民に公開することは非常に重要だと思います。
長岡市では、決算書は公表していますが、事務事業の公開までは実施していません。決算書では大まかにどんな事業にどれくらい税金を投入したかが、記載してありますが、具体的にどんな事業なのか?といったことは記載されておらず、実際にどのようなことに税金が投入されているのかが、よく分かりません。
私は具体的な事業にどれくらい税金が投入されているかを知りたいと思っています。事務事業単位で公開されれば、より具体的に税金の使い途が分かるため、市民としては安心できます。
他の自治体では、事務事業評価シートという形で、事務事業を公開しているようですが、事務事業評価は、磯田市長も6月の定例会で答弁されたように、職員の負担が大きい作業だと思います。特に職員が自己評価を付けるところが非常に負担だと思いますので、自己評価はしなくても良いと思います。そうすることで、事務事業を公開する負担は軽くなると思います。
私が求めていることは、具体的にどんな事業にどれくらい税金が投入されたかを知りたいだけなので、自己評価等はしなくても問題ないです。事務事業を公開することで、市民の間で、この事業は要る、要らないといった議論が活発になると思います。そのことが、長岡市の行政運営をより良くし、長岡の未来を明るくすることに繋がると思いますので、事務事業の公開の実施をお願いいたします。
○○さんが、長岡市の未来が明るくなるようにとお考えであることを、嬉しく思います。私も市長として同じ気持ちです。
人口減少が進む今後、市の財源確保はより厳しさを増すと考えられますので、施策や事業の成果を検証し、その見直しに積極的に取り組んでいくことは、これからの市政の重要な課題であると考えています。このため、税金の使い道を分かりやすく公開し、市民のみなさんの声を政策や施策の立案にいっそう反映できるよう、まずは、事業を実施している私たちがその成果検証に用いているデータを公開できるよう、仕組みを検討しています。
また、少し時間がかかりますが、先進のデジタル技術なども活用し、効率的・効果的にデータの整理や公開ができるような新しい事務事業の評価システムの構築についても、調査・研究を進めたいと考えています。(令和6年8月)
担当:行政管理課
電話:0258-39-2208 FAX:0258-39-2279 メール:gyoukan@city.nagaoka.lg.jp
①左岸バイパスと工場地帯を繋ぐ新しく出来た道路での長岡花火まつりのときの路駐が十数台とまっていて、すれ違ったりふつうに走行する車の妨げになっていて迷惑でした。8/2の1日目は打ち上げ開始すぐあたりにパトカーが来て注意喚起し、いなくなりましたが、すぐまた路駐がありました。8/3は、始まりからすでに路駐だらけでした。どうにか整備してほしいです。
②婚姻届で写真をとる背景が6年前、自分たちがとったものとずっと同じです。1年毎とかに変えるとおもしろいのではないでしょうか?
③学区変更をもっとやりやすくしてほしい。
④子ども医療費無料化、お願いします。
長岡まつり大花火大会における路上駐車の対策は、重要な課題として認識しております。今年は、ご指摘いただいた左岸バイパスから北スマートIC付近における市道沿いにおいて、路上駐車禁止の看板を設置するとともに、長岡警察署に巡回を依頼しました。来年の開催に向け、今年の状況を検証し、長岡警察署と情報共有しながら、大花火大会主催の一般財団法人長岡花火財団で一層の対策に努めていきます。
次に、アオーレ長岡の記念撮影スポットについては、婚姻の届出をされる皆さんからご利用いただいているところです。ウエディングブーケをデザインしたもので、平成24年のアオーレ長岡オープンを記念して設置したものですが、○○さんのご意見を今後の参考にさせていただきたいと思います。
学区外就学許可については、○○町は長岡市立学校通学区域規則で○○小学校が指定校になっています。指定校とは別に許可校を設定するには、まず、町内等の合意を得て要望書を提出していただき、その後、通学区域審議会で審議します。この一連の手続きについて個別に説明させていただきたいことから、お手数をおかけしますが学務課にお問い合わせくださるようお願いします。
最後に、子どもの医療費無償化について、小さなお子さんを複数人連れて受診されるご苦労、また医療費の負担を心配されるお気持ちはよくわかります。子どもの医療費は、他の医療費助成制度と同様に受益者負担の公平性の観点から一部負担金を定めており、将来にわたって制度を安定的に維持するためにも負担をお願いしております。本来、どこに住んでいても同じ助成が受けられる制度が望ましいと考えており、全国一律での無償化が実現するよう、国に対して要望しております。(令和6年8月)
①担当:観光事業課
電話:0258-39-2221 FAX:0258-39-3234 メール:matsuri@city.nagaoka.lg.jp
②担当:市民窓口サービス課
電話:0258-39-7510 FAX:0258-39-7509 メール:shimin_mado@city.nagaoka.lg.jp
③担当:学務課
電話:0258-39-2239 FAX:0258-39-2382 メール:gakumu@kome100.ne.jp
④担当:福祉課
電話:0258-39-2319 FAX:0258-39-2256 メール:fukushika@city.nagaoka.lg.jp
以前市長への手紙で共産党のホームページ上で共産党が与党の地方自治体と掲載されている事を質したところ、市長より「あずかり知りません」と回答がありましたが、納得できかねますので、改めて幾つかご質問させて頂きます。公人で在らせられる長岡市長には公開質問状である以上、昨今、SNS等のメディア等で公開される事も考慮の上、誠意あるご回答を切望いたします。
1 国政政党である日本共産党が公開されているホームページに磯田長岡 市長の許可なく、日本共産党が与党の自治体として長岡市と磯田達伸と個人名を掲載したのですか?
2 磯田市長の許可なく共産党のホームページに掲載されたのであれば無許可掲載として日本共産党を訴えるべきと考えますがその意思がありますか?
3 前回、長岡市長選挙が近づくと人知れず掲載したホームページから削除し、選挙戦が終わり、ほとぼりが冷めたころを見計らって、再度掲載されたことがありましたが今回も同じことが繰り返されない何か保証はありますか?
前回もお答えしましたとおり、市政においては特定の政党に寄ることなく、市民の声を第一にすべきと考えており、あらゆる政党からの公認や推薦は受けておりません。
ご指摘の記載は既に削除されているようですが、日本共産党がホームページにどのような掲載をしたとしても、私のこうした政治姿勢や考えが変わることはございませんので、ご理解いただきたいと思います。
引き続き、偏ることなく幅広に市民の声を聞き、真摯に考え、市民福祉の向上に努めることが私の責務と考えます。
担当:秘書課
電話:0258-39-2200 FAX:0258-39-2475 メール:hisyo@city.nagaoka.lg.jp
柏崎刈羽原発の再稼働可否の問題が議論されてますが、事故を起こしたら近隣住民の避難や移転が必要な原子力発電所は、設置自体が憲法22条の「居住の自由」を侵害する違法なものです。また、建築基準法第1条の「国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的にする。」にも違反するものです。原子力発電所は核兵器と同様のもので、あってはならないものです。事故があれば、ほとんど離散して長岡に戻る人はいません。
早急に、長岡は再稼働反対以上に廃炉の考えを表明してください。
原子力災害を心配されるお気持ちはよくわかります。
多くの市民の皆さんが柏崎刈羽原発の再稼働に不安を抱えていることから、私が代表幹事を務め、県内30市町村が参加する「市町村による原子力安全対策に関する研究会」において、原発の安全対策や防災対策の向上など、山積する課題解決に全力で取り組むよう、直接、国、新潟県、東京電力に強く求めております。
そして、7月15日にハイブ長岡で開催された「柏崎刈羽原子力発電所に係る国の取組みに関する県民説明会」において、参加者から多くの不安の声が上がったことからも、柏崎刈羽原発の安全対策や防災対策に対する多くの課題や懸念が解決されていない現段階においては、再稼働の是非の議論を進める状況ではないと考えております。
担当:原子力安全対策室
電話:0258-39-2305 FAX:0258-39-2309 メール:gen-an@city.nagaoka.lg.jp
先ごろ、転勤で長岡市に居を構えました。水道利用申し込みをしたところ、口座引き落としもしくは、コンビニ払いしか対応していない。しかも口座引き落としは市内に支店のある銀行のみ。今の時代カード引き落としすらできない。申し込みもいまだに3枚複写の申込書。インターネットからの申し込みすらできない。ちなみに手続き不備で申し込みし直しも3度目。市のほうにも負担をかけてしまいました。業務を変える事への抵抗があるのでしょうか、業務の効率を意識するとともに利用者の利便性を意識してもらいたい。そのようなことを考えることができる職員が増えれば、長岡市はもっと住みやすい街となると思います。
お客様サービスの向上は大切な視点だと認識しています。早速、ホームページの活用によるサービス改善など、できることから検討に着手するよう担当者に指示しました。
水道事業は、給水収益による独立採算で運営しています。しかし、地方では現在、人口減少に伴い年々収益が減少し水道の経営は厳しさを増しています。
収益力の高い首都圏の水道事業のように、DXやクレジットカード決済を取り入れたり、取扱金融機関を拡大するなど、サービス向上をはかりたい気持ちは強いものの、多額のコストを伴う場合が多いのも現実です。収益が減る中でのコスト上昇は水道料金の値上げにつながりますので、利便性向上とのバランスを慎重に考えると、直ちに実現するのは難しい状況です。
しかし、○○さんのご提案のとおり、時代の変化に合わせて利便性と業務効率を高めていくことは重要な視点と捉えておりますので、経営努力による収支改善などと合わせながら、前向きに取り組んでまいります。(令和6年7月)
担当:業務課
電話:0258-34-1412 FAX:0258-36-4432 メール:gyomu@m2.nct9.ne.jp
浦の河川公園南端に結構な大きさの池があります。現在ここでの釣りが有料になっておりますが、これを無料開放して頂けないでしょうか?
元々この公園は旧越路町時代に整備されたもので、当時は釣りも無料でした。週末ともなると多くのヘラブナ釣り師の竿が並び、子供連れの姿も多くのどかな光景が広がっておりました。私もずいぶん通わせてもらいました。
それが越路町が長岡市に合併されると共に魚沼漁協の「ここは有料 600円」の看板が立って。池の整備に魚沼漁協は何も関わっておりませんし、放流事業とも無関係な場所です。以降、当たり前に誰も行かなくなりました。今ではその立て看板の一つも草木に覆われて見えなくなっており、寂寥感が漂っています。池の水も以前より明らかに澱んできています。なぜ越路町が長岡市になると有料になるのでしょうか?
大人の事情が色々あるのでしょうが、だからこそ市長の一刀両断大岡裁きが必要なのでは、と思えてこの手紙にさせていただきました。釣りファンは潜在的に多くいます。ささやかな庶民の娯楽を叶えていただければ幸いです。
ps. 例えば高齢者と子供連れは無料、なんてのもアリかも知れませんが、願わくば全面開放していただきたいです。
○○さん及び釣りファンの方々が、越路河川公園にてヘラブナ釣りを楽しみにしていたことはよくわかります。
旧越路町時代、週末になると多くのヘラブナ釣り師の竿が並び、子ども連れの姿も多くのどかな光景が広がっていた姿をご覧になっておれば、現在の状況は正に寂寥感漂うものと思われます。
今回ご指摘の池についてですが、取扱いは池ではなく脇を流れている焼田川の支流となります。
魚沼漁業協同組合に確認したところ、現在も秋にヘラブナを放流する活動を行っており、昭和60年の公園開園時より有料の取扱いは変わっていないということでした。
取扱いは通常の河川と変わらないため、遊漁券をお買い求めいただきファンの方を含め、釣りを楽しんでいただければと思います。(令和6年6月)
担当:南部地域事務所(越路支所内)
電話:0258-92-5901 FAX:0258-92-6942 メール:nambuchiiki@city.nagaoka.lg.jp
○○方面隊の春季消防団演習にて軽度の熱中症になった団員がでました。発症は閉会式中です。
それほど強い日差しではないものの25度を超える予報で、せめて半袖にすることを許可していれば防げたもの。これは「あとは閉会式だけだから」という安易な考えによるところもあったもよう。気温の上がる時間に「集まれ!」の駆け足をさせ、集合による体温上昇した人間の熱気がこもるため 実は閉会式の時間帯が一番危険であります。
「適宣水分を取るように」放送を流してましたけど、待機場所の都合上、飲みに行きにくい雰囲気であること、待機場所はグラウンド端で体温を下げられる場所ではないことも関係するのでしょう。
熱中症はまず、体温を下げられる環境が必要です。そのうえで、水分補給により発汗促進、脱水予防となります。執行員たちは水だけでなんとかなると思っているのでしょうか?○○市議も見ていたはずですが「団員の生命・健康」を守る気はないのでしょうか。
「消防団員の健康」が守れなくては「市民の生命財産」は守れません。「団員の生命・健康」を守る「教育・指示」を管理職の方がたへ行うことを切実に要望いたします。
このたびの消防団春季消防演習で、団員が体調を崩すような事態になりましたことに対し、お詫び申し上げます。
消防団の活動服は、災害活動時の安全管理、事故防止のため、肌の露出を少なくした長袖仕様としており、訓練においても災害活動を想定し基本的には夏場であっても上衣を着用して行っております。しかし、近年の気候変動により、早い時期から気温の高い日が多くなることが予想される中、○○さんのおっしゃるとおり、時には上衣を脱ぐなどの配慮が必要であると考えます。
消防団活動の本来の目的を果たすために、団員の体調管理は欠かすことのできない非常に重要なものです。
今後各種消防団行事を実施する際には、団員の体調管理についてもさらに対策を強化して計画します。また、消防団幹部の会議や研修などにおいて、熱中症に関する知識の共有や、体調管理に十分注意するよう周知徹底を行い、気象状況に合わせて、服装や休憩等に配慮いたします。(令和6年6月)
担当:与板消防署
電話:0258-72-2572 FAX:0258-72-4569 メール:yit-syobo@city.nagaoka.lg.jp
日本共産党との関係についてお訊ね致します。日本共産党ホームページには同党が与党の自治体として長岡市が記載されており、関係は支援とありますがご存知でしょうか。又今後同党との関係はどの様にされるのか市長のお考えをお聞かせ願います。
日本共産党のホームページに長岡市と私の名前が掲載されていることは存じておりませんでした。市政の運営については、国政とは異なり、特定の政党に寄ることなく、幅広く市民の意見を聞くことが重要だと考えてきました。従って、あらゆる政党から公認や推薦は受けておりませんし、今後求める考えもありません。
引き続き、市民第一を旨とする「市民党」の立場に立って、市民福祉の向上に努めてまいります。(令和6年5月)
担当:秘書課
電話:0258-39-2200 FAX:0258-39-2475 メール:hisyo@city.nagaoka.lg.jp
私は近隣住民です。これ迄も問題提起をして来ました。
今だ改善されていない点について、再度のお願いです。
1. 「成人式」は別の場所でお願いします。
たとえば長岡市立劇場 等
<上記根拠の事例>
①5月3日(金)ナカドマ(ソトドマ含む)に多くの若者が滞留し、「ざわめき」が異常です。65デシベルは軽く超えていて、体感では80デシベル位です。騒音だった時間9:50~13:30
②これは長岡市が決めている騒音基準を、自らが違反している事になります。尚、「成人式」に限らず、人の「ざわめき」が出ると予想されるイベントについても同様です。
2. イスとテーブルは、21:00以降には片付けていただく事をお願いします。
<上記根拠の事例>
①5月3日(金)騒音だった時間21:50~0:30
②5月4日(土)騒音だった時間21:50~
特にこの日は、セブンイレブンの近くで、仲間10人位の若者男性の酔っぱらいが大声で叫んだり、歌を唄ったりして、1時間以上いました。
③平常時でも、金、土曜日はうるさいです。
<疑問に思う事>
①警備員は奥にいて、気が付かないのでしょうか?又、注意はしないのでしょうか?
②夜の時間帯に問題があり、未来創造ネットワークの終業時間である21:00には片付けていただきます。
この度は、成人式(二十歳のつどい)の開催にあたりご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。
式典前後および式典中、大きな音が発生しないよう、対象者へ帰宅を促すアナウンス等を行っておりました。しかし、ナカドマ・ソトドマに二十歳になられた方、その保護者が集い、再会の喜びの声が大きい音として発生してしまいました。
○○さんに不快な思いをさせてしまったこと、深くお詫びいたします。
なお、二十歳のつどいの会場につきましては、市民協働・交流の拠点であり、3,000人(対象者と保護者)を収容できる市の施設が限られることから、引き続きアオーレ長岡で開催したいと考えております。
今後、アオーレ長岡での二十歳のつどい開催にあたっては、これまでと同様ナカドマ内のスピーカーの音量調整を行い、他の対策を講じたうえで、大きな音が発生しないよう細心の注意を払って開催いたします。
なお、その他のイベントの開催にあたりましても、様々な対策をしてまいりましたが、今後も大きな音が発生しないよう細心の注意を払い、周辺にお住まいの皆様にご迷惑をおかけしないよう努めてまいります。
また、夜間のナカドマにつきまして、テーブル・イスをすべて撤去すれば人々が集まらなくなるという○○さんのお気持ちはよくわかりますが、必要とされる方もいらっしゃるため、すべて撤去することは難しいことをご理解ください。
ただし、5月3日や4日のように特に多くの若者が集まる日の夜間については、テーブル・イスをナカドマの奥側であるアリーナ付近を中心に数量を調整して配置し、周辺住民の皆様にご迷惑をかけるような行為を行わないよう、警備員による監視と注意喚起を強化してまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。(令和6年5月)
担当:子ども・子育て課
電話:0258-39-2300 FAX:0258-39-2605 メール:kodomo@city.nagaoka.lg.jp
担当:市民協働課(アオーレ交流)
電話:0258-39-2288 FAX:0258-39-2308 メール:aore@city.nagaoka.lg.jp
本日4月26日、前々から予約していたアオーレ長岡のシティホールDを17時からしようすることになっていました。予定より時間が空いたので、15時55分ごろにアオーレに到着したところ、先行の団体「○○」様が13時から16時まで同じ部屋を使用することになっていましたので、当日は、慣れないイベントだったということもあり、部屋が空いているようなら、早く使わせてほしいとおもい、「前の団体の利用が終わり次第早く使わせてほしい」と受付に打診し、了承を取り付けました。その後、まてどもまてども、「○○」様が部屋から出てくる様子はなく、事務局へ電話で問い合わせたところ、「17時迄延長している」との連絡が。ところが、アオーレの部屋利用の掲示には、13時から16時迄としか表示がありません。ちなみに、弊会は17時からの利用で予約しておいたはずなのに、掲示はなぜか18時からの利用になっていました。16時49分に、「○○」様が部屋から出られましたが、当方、17時から部屋を借りて準備をしたかったのに、「○○」様の鍵の返却が17時ジャストになってしまい、部屋を借りるのに当初予定時刻を過ぎてしまいました。そこで、部屋の鍵を返しに来た「○○」様の事務局であらせられる方に、「うちは17時から部屋を借りている」といったところ、「うちは17時迄部屋を借りている」といわれ、唖然としました。うちは17時から部屋を借りているのだから、通常の感覚でいえば、16時50分には、部屋の原状復帰を行い、おそくとも、16時55分には部屋を開けるべきではないかと。 要約すると、以下の問題点があげられます。1部屋使用の延長があったのにも関わらず、公の場で確認できる部屋の利用状況を表すボードに、その変更点が書かれていなかったこと。2うちの使用時間が、本来17時から借りるべきはずのものが18時と併記されていたこと。また、先方の鍵返却時に、相手様に、抗議をしたところ、アオーレの職員は、○○ばかりを我慢させ、時間通りに部屋の鍵を返却しなかった先方に対して、何も咎めがなかったこと。これは、私及び私の主催する団体に、アオーレ長岡をを使わせないようにしていると判断し、抗議のお手紙を差し上げた次第です。
基本的に、なるべくは、○○の団体が部屋を利用する際は、時間前に鍵を返却するようにしてますし、締め作業に時間がかかり、やむを得ず使用時間が過ぎてしまった場合は、まず先方及びアオーレ職員の方に、まずは謝罪するのが筋ではないでしょうか? それを、「○○」様の事務局の方は、一言の謝罪もなく、むしろ、我々の方が間違っているかのような威力をもってして、言論を封殺されました。なお、「○○」様は、その性質上、宗教団体の利用と思われます。公的な施設であるアオーレ長岡の施設を、宗教団体がその宗教的な目的のために利用することは正しい長岡市の施設の使い方といえるでしょうか。このような不公平な扱いをするのであれば、いっそ、私にアオーレを使うなと言っていただいたほうが、まだ納得いきます。侮辱です。以前、まちなかキャンパスの市民プロデュース講座の選出の仕方に、不公平を感じ、そのことを訴えましたが、これは、そのことへの報復でしょうか。 意図的なものではないというのならば、今後、同じような不公平なことが起きないように、改善していただきたい。つきましては、どのように改善するのか、明確にお答えください。
いつもアオーレ長岡をご利用いただきありがとうございます。
このたびはアオーレ長岡の利用に際して不快な思いをさせてしまい、申し訳ありませんでした。
○○さんと○○さんの前の利用者が利用時間を変更されたにも関わらず、利用案内の表示の修正を怠ってしまったことが原因と考えております。今後このようなことがないよう、変更の申し出を受け付けた時点で、正しい案内表示となるよう速やかに変更してまいります。
また、アオーレ長岡は時間の切れ間なく利用者が入れ替わることの多い施設であるため、施設を有効利用するとともに、利用者が気持ちよく利用いただくためには、○○さんのおっしゃるとおり、利用者がお互いに思いやりの気持ちを持って利用いただくことが大切です。アオーレ長岡スタッフからすべての利用者に対して、次の利用者へのスムーズな部屋の引き継ぎができるよう、ご協力いただきたい旨の声がけをしてまいります。
なお、ご指摘をいただきました宗教団体のアオーレ長岡の利用について、交流ホールは団体の会員の内部会議として利用いただくことは可能です。(令和6年4月)
担当:市民協働課<アオーレ交流>
電話:0258-39-2288 FAX:0258-39-2308 メール:aore@city.nagaoka.lg.jp
ウィキペディアは市町村検索では常にトップ、または上位表示されますが、なぜか、長岡市と検索すると、ウィキペディアの写真が寺泊のアメヤ横丁になっています。
長岡に関心がある方は、検索後、文章もそうですが、その写真を見て、長岡をイメージするはずです。市役所のHPはその点、素晴らしいと思います。ですが、肝心の上位表示される媒体がそのような写真構成だと、この媒体によって、他自治体と比較されることに大きな違和感を感じます。移住政策や交流人口対策にも影響を与えていると考えます。
もし、市長含め、行政の方がこの件に関し、民間の作業なのでタッチできない、もしくは作業手間取るようであれば、私の方に長岡のさまざまな美しい風景(花火と市街地、アオーレ、ミライエ、東山、西山と市街地の四季の眺め)等を送信していただき、こちらでWikipediaを編集しますので、ご返答願います。
このたび、ウィキペディアに掲載されている寺泊魚の市場通りの写真をご覧になり、違和感を覚えておられるとのことですが、ウィキペディアはインターネット百科事典として多くの人から利用されており、誰もが内容を編集できることが最大の特徴です。多くの人の考えや思いが集まってつくられているものだと思いますので、明らかに誤った情報が掲載されている場合を除いて、長岡市がウィキペディアの情報を編集すること、また、どなたかに編集をお願いすることは考えておりません。
長岡市は11の市町村が合併しとても広くなり、寺泊魚の市場通りをはじめ各地域の魅力も増えました。これからも、市ホームページやフェイスブックなど様々な媒体で長岡市の魅力を伝えてまいります。(令和6年4月)
担当:広報・魅力発信課
電話:0258-39-2202 FAX:0258-39-2272 メール:inf-prd@city.nagaoka.lg.jp
先月大学であった企画で、長くパレスチナ支援をされている写真家から現地のお話しを伺いながら、パレスチナ問題について学び、我々ができることを考えました。
ハマスのテロ行為は許されないことですが、パレスチナ側から見ればイスラエルのテロ行為で、多くの市民が命を落としていると考えるのではないでしょうか。難民キャンプにも度々イスラエル軍が侵入して、インフラを破壊して行くなど様々な困難を強いられているようです。飢餓や飲料水へのアクセスの問題も深刻です。様々な考え方や立場があるとは思いますが、個人的にはイスラエルがとってきた行動がハマスなどの戦闘グループを生んできたと考えています。
イスラエルは、国際法やパレスチナ人の人権を無視し続け、昨年10月7日以降既にパレスチナ人の死者数が3万人を超え、大多数が女性や子どもと報道されています。更に長岡市人口を有に超えるパレスチナ難民が発生しています。
新潟県では、県議会、新潟市議会、新発田市議会がガザ地区における平和実現の決議書を発表していますが、他にはまだないようです。
長岡市には、SDGsハブ大学である長岡技術科学大学があり、拉致問題もあり、人権問題に対し関心が高いと考えています。長岡市もぜひ、同等の決議と、決議を英語等多国語でも発表していただきたいと考えています。先の決議発表は日本語だけのようです。日本語だけでは、アピール力が弱いと考えています。
ご検討のほど、よろしくお願いいたします。
ガザ地区における平和の実現を早期に求める決議をし、多国語で発表してほしいというご意見をいただきました。
決議は、議会に権限があるものですので、○○様からのご要望については、請願として議会に提出いただければ、決議の採択を審査します。詳しくは、議会事務局までお問い合わせください。(令和6年4月)
担当:議会総務課
電話:0258-39-2244 FAX:0258-32-0827 メール:gikai@city.nagaoka.lg.jp
このページの担当
- 市民窓口サービス課
- 〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2246 FAX:0258-39-7509