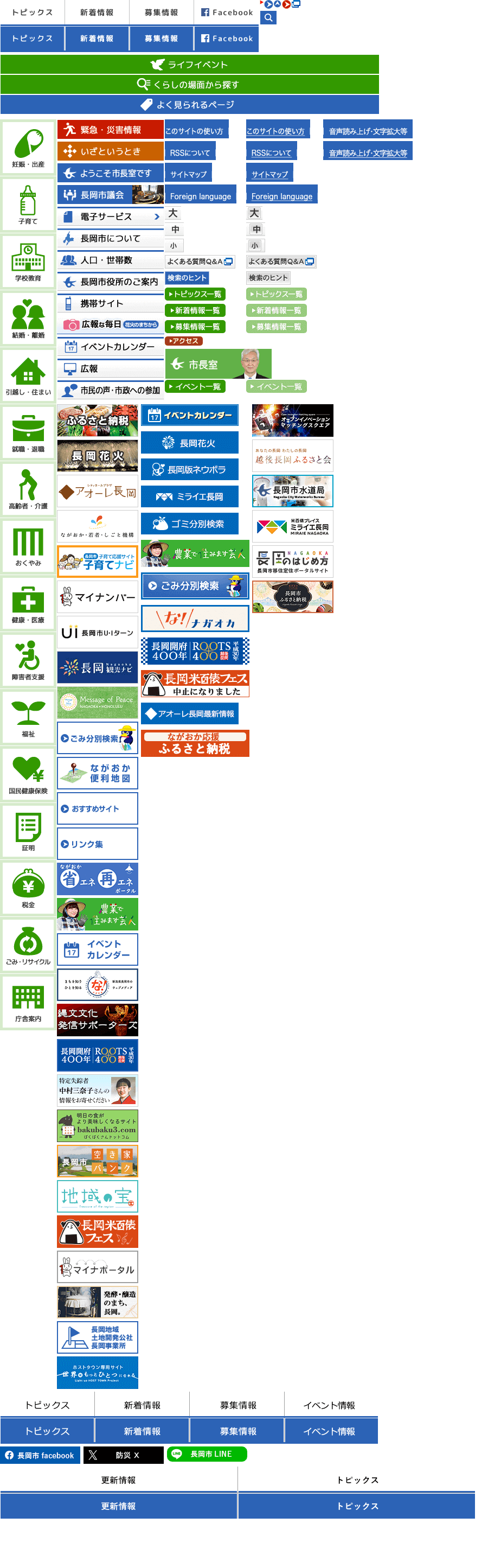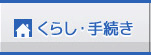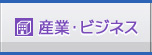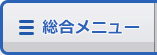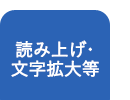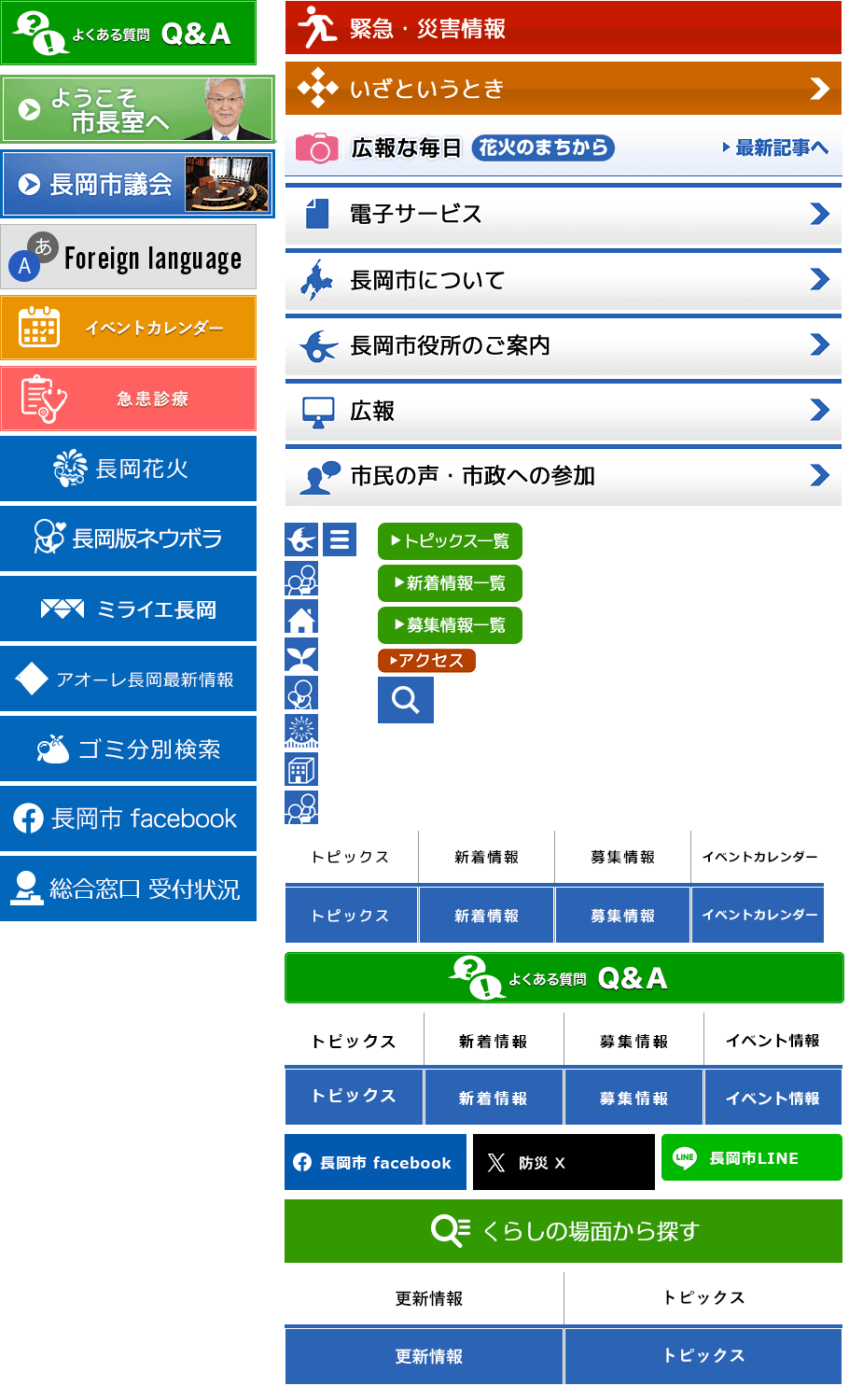令和6年度 主なご意見と回答-健康・福祉
最終更新日 2025年6月20日
小中学校の(外周or校庭)ウォーキングコース(歩道)化を検討して下さい。
長岡市は高齢化が顕著で65歳以上の3割を占めています。健康保持増進の観点から要介護状態の予防、介護保険の費用低減は喫緊の課題であります。住民にとって健康保持増進は、運動習慣の定着による健康寿命の増進に寄与します。特に、身近な所で気軽に運動実施をする環境整備は欠かせないのではないでしょうか? 運動の中で特にウォーキングは全身運動・有酸素運動にとても良い効果があります。それを行う機会を整えてほしいと考えます。
具体的には、市内の小中学校において、歩道や車道にガードレール柵、ポールなどを設置し車道との区別を図る。または、同敷地〜グラウンド外側一周にアスファルト、人工芝、陸上競技場トラック2レーン、土の圧着でもいいので、他の場所と区別がわかるように整備する案があります。可能であれば、途中で休憩できる可動式のベンチがあると良いかもしれません。
デメリットは、整備費用と管轄部署です。道路であれば県道や市道など管轄外かもしれません。敷地内であれば、市立なので、おそらく市の予算?教育委員会の予算?なのかもしれません。管理管轄するする部署をいくつもまたぐかもしれません。不勉強ですみません。冬場の除雪作業で消雪パイプがなければ重機除雪が手間、難しいこともあるかもしれません。また、冬場の利用ができず効果は半年強かもしれません。費用対効果も疑問です。
メリットはその場所を開放していただければ、地域住民の運動機会、特に65歳以上の高齢者が想定されます。体が少し弱ってフレイルやサルコペニアになってもまだ散歩に出られる、万一要介護状態になっても介護サービスにて外出や気分転換をする機会にもなります。可能であれば、要介護状態にある方が使う歩行器やシルバーカー、車椅子などが安全に通行できるような整備があるとより集まりやすいと思います。人が集まれば自然と交流機会もコミュニティもできるかもしれません。もちろん、時間帯を区切れば(世代別での使用時間のゾーンニング)、児童・生徒の安全なマラソン、部活動の地域移行の活動での活用、散策機会にも寄与することでしょう。まずは、人口の多い旧長岡市で始めはどうでしょうか。ぜひ、ご検討下さい。
○○さんがおっしゃるとおり、運動は生活習慣病を予防し、健康寿命の延伸につながる重要な要素であると認識しています。
ご要望をいただきましたように、小中学校の外周や校庭にウォーキングコースがあれば、地域住民の皆様の学校の周りを歩く姿が増える可能性もあるかと思います。
しかしながら、学校は子どもたちが毎日安全で安心して過ごし、日々の教育活動を行っていく場所であり、校庭や敷地、また学校施設の周辺において、ご提案のような施設を整備することは、現在、考えておりません。
ご要望にお応えできず申し訳ありませんが、ご理解いただきますようお願いします。
なお、住民の皆様に学校のグラウンドや体育館をご利用いただける制度として、「学校開放」があります。地域の方々とグループを作り、運動やスポーツを楽しむためにご利用いただくことができますので、ぜひ、ご利用ください。
また、長岡市では従来から、誰もが気軽に運動を始められるように、地域の名所や旧跡を巡る28コースのウォーキングマップの活用を進めているところです。今後、さらにコースを拡充するとともに、市民の皆様への周知に努めていきます。
それに加え、スマートフォンで歩数や食事、体重などの記録を管理できる健康アプリ「ながおかウェルネスチャレンジ」を導入し、市民の運動習慣につなげ、健康寿命の延伸を目指します。(令和7年2月)
担当:教育施設課
電話:0258-39-2236 FAX:0258-39-2271 メール:kyosi@kome100.ne.jp
担当:健康増進課
電話:0258-39-7508 FAX:0258-39-5222 メール:kenkou@city.nagaoka.lg.jp
政府が補正予算を11月22日に閣議決定し、12月17日に補正予算が成立しましたが、他の県は給付金を配布し始めていますが、長岡市は動いてる気配がないのですが、どうするおつもりなのでしょう?給付金を待っている方々は、たくさんいると思います。3万円でも助かるのです。年越し、正月、いろいろなことが値上がりでどうしょうもないのですがせめて見通しだけでも教えていただけないでしょうか?
住民税非課税世帯への給付金に関する国の補正予算の成立を受け、長岡市は、給付に向けた各種の準備を鋭意進めており、給付金の支給に必要な費用の予算を専決処分で決定したところです。
日程につきましては、3月中旬から給付金の対象世帯へ御案内をお送りし、4月上旬から順次支給を行う予定です。
その他給付の詳細につきましては、御案内できる準備ができましたら、市のホームページなどでお知らせいたします。(令和6年12月)
担当:非課税世帯等臨時特別給付金室
電話:0258-39-2347 FAX:0258-39-2256 メール:fukushi-kyuuhu@city.nagaoka.lg.jp
長岡では在宅介護者支援金の制度がありますがそのことについてです。長岡独自の条例で素晴らしい制度だと思いますが、負担がケアマネに重すぎます。手続き等はケアマネ任せでありますし、少しでも手続きが違うと職員から厳しい言葉で責められます。ケアマネは、この制度では報酬はなく完璧なボランティアでやっていますが責任が重すぎます。役所職員が本来やる事を無償でやっているのに、少しでも間違えたら責められたり、会社の方向性について散々な事を言われたことがあります。この様な事があるのならば無償でなんでするのかと思っています。今後も無償で押し付けるのか、少しでも報酬をもらい責任感をもち手続きするのかどうかと気になり書き込みしました。市長の考えが聞ければと思いましたので宜しくお願いします。
日ごろから、在宅介護者支援金事業にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。
日々、ケアマネジャーとして様々な業務を行われる中、在宅介護者支援金事務について負担に思われる○○さんのお気持ちはよくわかります。市では、これまでも当該事業について「有償化しても法人の口座に振り込まれれば、ケアマネージャーのモチベーションには繋がらない」「無償化というよりは、事務を効率的に行えるようにして欲しい」などのご意見をいただいております。
それらを踏まえて、今年11月からは一部の事務においてロゴフォームを用いた申請の運用を開始したほか、今後は共有フォルダを構築し、事業者の皆様から市への提出物をデータで格納いただくなど、業務の効率化を図るしくみを検討しているところです。
今後も、在宅介護事業者のご意見を伺いながら、皆様の負担を少しでも軽減するよう取り組んでまいりますので、ご理解いただきたいと思います。(令和6年11月)
担当:長寿はつらつ課
電話:0258-39-2268 FAX:0258-39-2603 メール:hatsuratsu@city.nagaoka.lg.jp
私は重度の障害を持つ息子を持つシングルマザーです。いつも色んな手当のおかげで生活を送ることができています。本当にありがとうございます。
しかし、困ったことがあります。住まいを見つけ、暮らしていくことが困難です。離婚後、実家に戻ってきて親と一緒に暮らしていますが、長らく実家を出て暮らしていたため、車を停める駐車場や部屋がありません。仕事をして貯金をして出るつもりでしたが途中で息子の障害が分かり、病院や支援所の送迎など色んなことでフルタイムで働くことが困難になりました。
そうすると収入だけではとてもじゃありませんが貯金できる収入はありません。市営住宅に住もうと思いましたが、障害のためお隣、上下の方に奇声などで間違いなくご迷惑をおかけします。それを分かっていながら住むことはできません。クレームも勿論もらいますし、理解してくれない方もいるはずだからです。実家をリフォームするにも、無駄に坪数が大きい家で市の助成では全く足りません。(ましてやローンを組めません)
障害のある家族がいる家庭が周りに迷惑をかけず暮らすためには一軒家のように周りに音が響かない家が必要です。ローンも組めない私のような家庭は、貸家を借りるしかない状態ですが貸家は高いです。ましてや安い貸家は築年数が古いため、障害のある息子にとってはバリアフリーでないことが介助をするにも困難です。暮らしやすい構造、作りの家は高すぎて払えません。
そのため、家賃補助の制度を作って欲しいです。自治体によっては家賃補助が出るところがあるため本当は引越したいですが、引っ越すと援助してもらえる環境でないため、ひとり親としてはそれも難しいです。どうかご検討いただけたらと思います。
ずっとこの想いを持って生活していましたが限界を感じています。他にも同じことで悩んでるご家庭が必ずあります。よろしくお願いいたします。
重度の障害を持つお子さんを育てながらお仕事もされ、そのご苦労はいかばかりかとお察しいたします。
長岡市では、ホームレスの方などを対象とした民間賃貸住宅の家賃の補助制度はありますが、他に同様の制度はないことをご理解ください。なお、住宅リフォームであれば、住民税非課税世帯対象で、50万円を上限に費用の4分の3を補助する、障害者向けのリフォーム補助があります。担当課(福祉課障害活動係 電話:39-2343)までご相談ください。
また、障害者世帯を対象にした無利子の貸付制度があります。こちらの相談窓口は、長岡市社会福祉協議会(地域福祉課 電話 33-6000)です。(令和6年10月)
担当:福祉課 障害者福祉
電話:0258-39-2218 FAX:0258-39-2343 メール:fukushika@city.nagaoka.lg.jp
このページの担当
- 市民窓口サービス課
- 〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2246 FAX:0258-39-7509