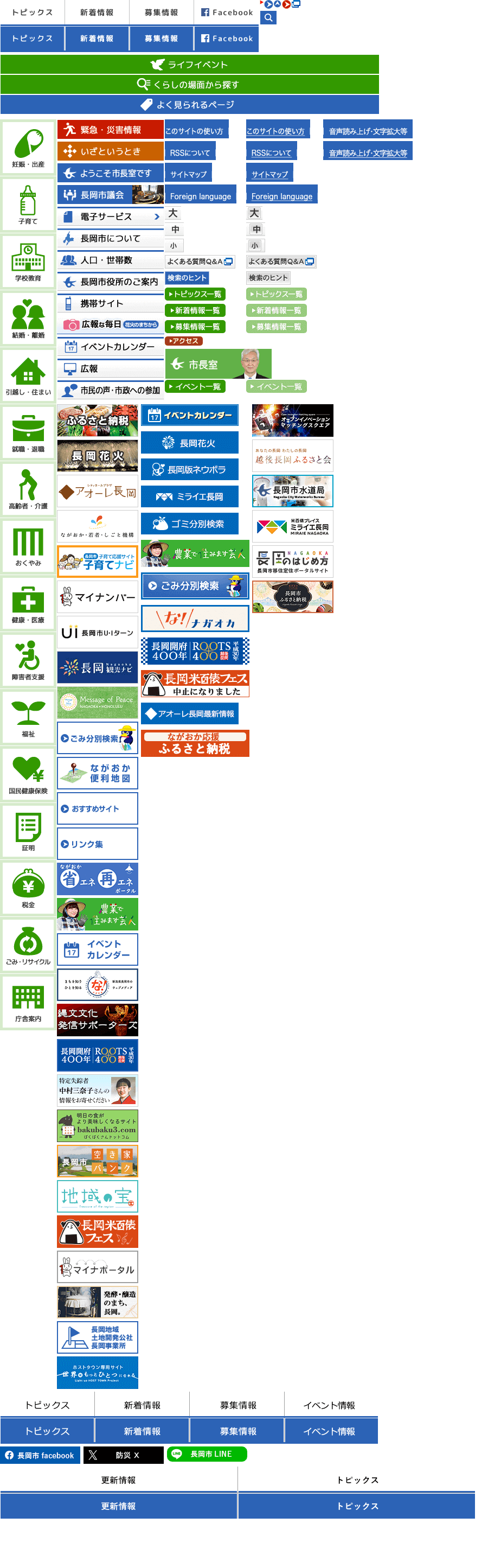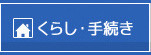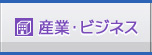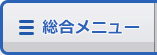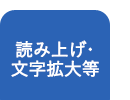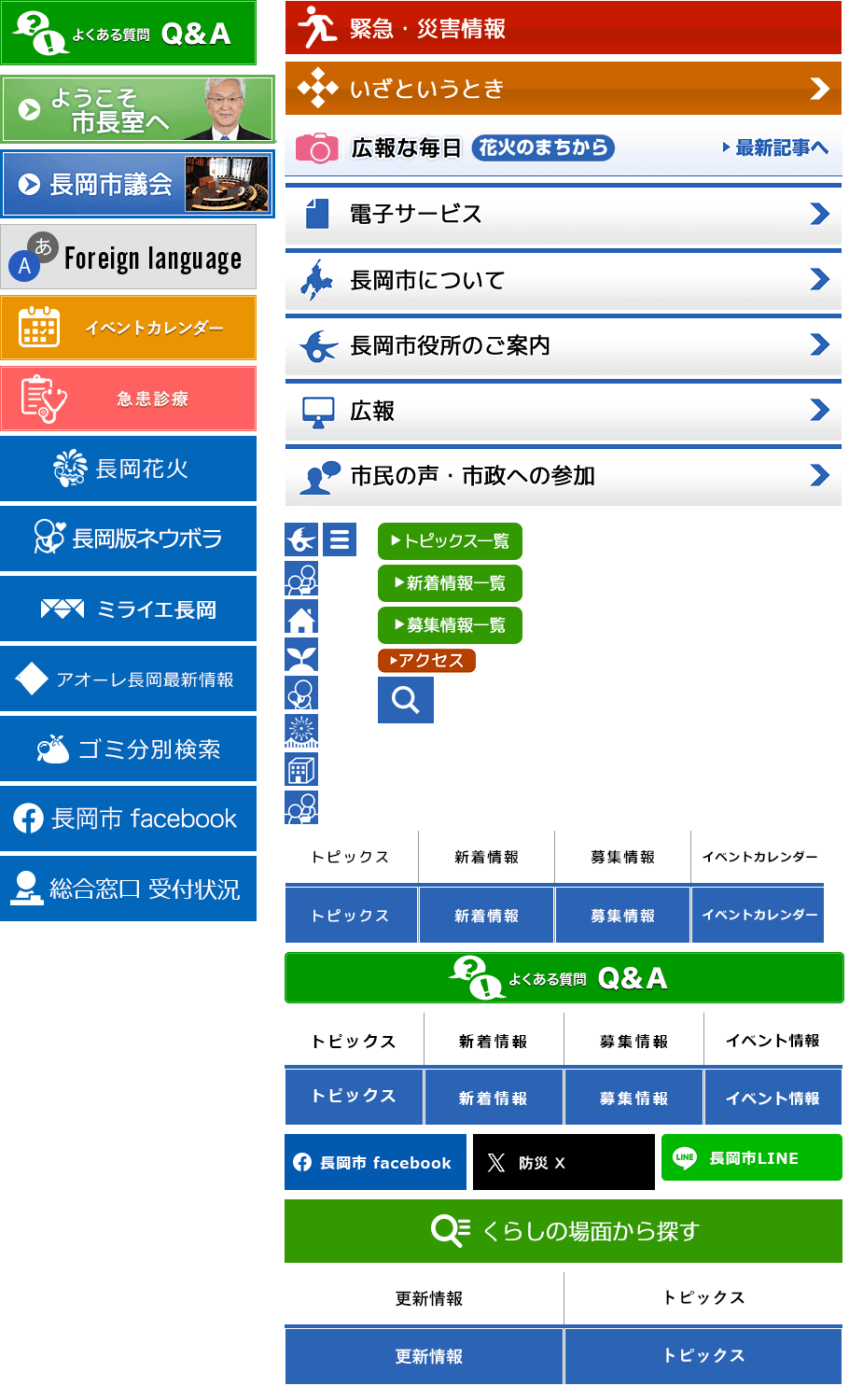長岡戦災資料館 -トピックス-
最終更新日 2025年9月11日
「教育版マインクラフトを活用して長岡空襲の史実と復興の歴史を学ぼう」を開催しました(掲載日R7.8.21)
8月9、10日の2日間、ミライエ長岡で「教育版マインクラフトを活用して長岡空襲の史実と復興の歴史を学ぼう」を開催し、19組の小学生と親子から参加いただきました。
1日目は、長岡戦災資料館運営ボランティア・語り部として活躍されている、谷芳夫さんから長岡空襲の史実について、語っていただきました。参加された子どもたちは谷さんのお話を真剣に聞きながらメモをとっていました。「当たり前のことは当たり前ではない」「感謝を忘れずに」という、谷さんの言葉が子どもたちの心に響いたようです。
続いて、令和3,4年と長岡市が取り組んだ「白黒写真のカラー化事業」に御協力いただいた東京大学渡邉英徳教授からも、戦争のこと、戦後のことを漫画を引用しながら講話いただきました。白黒写真がカラーになると写真の中の少年は、まるで息をしているような表情となり、子どもたちは自分事として捉えやすかったようです。
 |
 |
午前中の講話を聴いたあとはいよいよマインクラフト制作。今回は、空襲時に焼け残った長岡市役所、宝田公園・公会堂、長岡国民学校、平潟神社、長岡日赤病院をさまざまな文献を確認しながら制作しました。子どもたちは初対面とは思えないほど上手にコミュニケーションを取りながら共同作業を進めました。
2日目は、「復興」をテーマに講話をお聞きしました。講師は、長岡市立科学博物館金垣館長。長岡空襲の後、家屋の復旧が早かったこと、復興宝くじの売り上げは、すべて建物の再建に使われたこと、当時の長岡市が、市民の協力により、なりふり構わず復興事業を進めたことなどをお話いただきました。驚いたことに、1日目の学習を踏まえ、自宅でさらに再建する建物について調べたり、実際に建造物に足を運んだ親子がいたこと。能動的な学習にしっかりと繋がっていました。
いよいよ、成果発表のとき。ほぼ満席のミライエステップで子どもたちは2日間で感じたことを堂々と発表しました。「当たり前は当たり前じゃないんだ」「平和を作るために戦争の悲惨さについて学び、考えることが大切」など、参加した子どもたちの心の変化を感じることができました。
市では、今後も講話や紙芝居といった方法とともに、新しいツールも活用しながら、次の世代に戦争の悲惨さや平和の尊さを伝えていきます。
 |
 |
第2回長岡空襲の体験を聞く会を開催しました(掲載日R7.8.21)
7月13日(日)、第2回「長岡空襲の体験を聞く会」が開催され、約55名の方が参加されました。今回は、武笠和子さん、野本九萬雄さんから貴重な体験講話を伺いました。
武笠さんは当時7歳。空襲の夜、焼け野原になった街を歩き、溶けてしまった食器など、戦後の困窮を目の当たりにしました。「あの日の記憶は、今も鮮明に蘇ります。戦争は、決して繰り返してはいけないのです。」と、力強い言葉で語られました。
野本さんは当時8歳。長岡空襲に遭遇し、避難中に焼夷弾が降り注ぐ恐怖を体験しました。長岡の街が炎に包まれ、多くの焼死体を見たという衝撃的な体験を語られました。「あの時、私たちは『欲しがりません、勝つまでは』という言葉を聞かされました。しかし、精神論だけでは戦争は止められません。戦争は、どんなものでも奪ってしまうのです。」と、戦争の恐ろしさを改めて認識させられる言葉でした。
 |
 |
続いて、今井和江さんから長岡空襲紙芝居「思い出の記」を上演していただきました。今井さんの迫力ある感情が込められた公演は、当時の様子を鮮やかに描き出し、来場者も終始真剣な表情で聞き入っていました。

当館では、今後も講話や紙芝居といった方法等を活用しながら、次の世代に戦争の悲惨さや平和の尊さを伝え続けていきます。戦争の記憶を風化させないため、ぜひ当館へお越しください。
長岡空襲体験画展と合わせ、富山大空襲関連資料展を開催しました(掲載日R7.6.3)
5月17日(土)から25日(日)の9日間、長岡空襲80年特別事業として富山大空襲関連資料展を開催しました。
富山大空襲は1945(昭和20)年8月2日未明、アメリカのB29爆撃機により市街地の99.5%が焼き尽くされ、亡くなった方は2,700人を超え、地方都市の人口比で最も多くの犠牲者を出しました。
展示の中には、当時20歳だった女性がクレヨンで描いた25枚の体験絵日記もあり、凄惨な富山大空襲の場面が描かれていました。
長岡空襲体験画展は6月15日(日)まで開催しています。空襲の悲惨さや、戦争の恐ろしさをあらためて認識する機会にされてはいかがでしょうか。

長岡空襲体験画展を開催しています(掲載日R7.5.7)
4月26日(土)、19回目となる長岡空襲体験画展が始まりました。
当館の活動に御協力くださっているボランティアのかたや、当館とかかわりが深いかたの作品を中心に56点の体験画を選定し、作者別に展示しています。開催は6月15日(日)までとなります。
長岡空襲体験画は、平成18年に長岡市政100周年の記念事業として収集を開始した、当館の活動を代表する資料です。長岡の地に容赦なく襲い掛かった空襲について、写真では表現できない情景や作者が作品に込めた平和への思いをぜひ御覧にお越しください。
長岡空襲及び戦後から80年目を迎える今年は、特別事業の一つとして、広島「次世代と描く原爆の絵」展を、同会場にて5月11日(日)まで開催しています。広島の高校生が被爆体験証言者の話を聞き、打ち合わせを重ねながら描いた絵のパネルを、被爆体験とその体験の継承の形として展示します。
また、会期の後半、5月17日(土)から25日(日)の間は、特別事業として、富山大空襲の体験者の絵日記など展示も予定しています。
近年、戦争を知る世代が少なくなりつつあり、空襲体験をいかに伝え、後世へ引き継いでいくかが大きな課題となっています。これを機に、空襲の体験と継承について、ぜひお考えください。
 |
 |
このページの担当
- 庶務課
- 〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2203 FAX:0258-39-2275